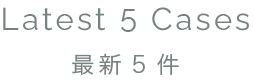腹腔内陰睾(潜在精巣)
陰睾って??
雄の犬猫の去勢手術は、全国様々な病院で一般的に行われている予防手術です。
通常、精巣はお腹の外の陰嚢と呼ばれる袋に位置しています。もともとはお腹の中で発達する臓器ですが、犬は生後30日から2-3ヶ月で、猫は生後30日以内(遅くとも2ヶ月以内)陰嚢内に移動します。これを精巣下降といいます。
ですが、この精巣下降の過程で、精巣がお腹の中や鼠径部にとどまってしまう「陰睾・潜在精巣」の状態になってしまう方が一定数います。
通常の精巣は、体外に位置していることから、体温よりもやや低い温度で維持され、これが精巣の働きを助けています。ですが陰睾の場合、体温と同等の温度帯にずっとどまってしまうことから、精巣の働きや細胞に悪影響を与え、精巣腫瘍の発生率が上がってしまうことがわかっています。
陰睾である場合は、より去勢の手術が望ましく、今後の病気の予防が必要となります。
腹腔鏡(手術内視鏡・ラパロ)
鼠蹊部の陰睾であれば、通常の去勢手術のように陰茎もしくは鼠蹊部の皮膚を切皮し、精巣を取り出します。ですが腹腔内陰睾の場合は腹壁(腹筋)を開けて、お腹の中から精巣を探して取りだすため、比較しても体への手術侵襲が高くなります。体の大きな大型犬であれば、なおさら傷はおおきくなりますし、消化管にまぎれて精巣が見つかりづらく、探索に時間を要することもおおいです。
通常は上記のように大きく開腹しての手術になりますが、動物医療センター元麻布を始め、AMCグループ・小滝橋動物病院グループでは、腹腔鏡(手術内視鏡、ラパロ)を用いての手術が可能です。
腹腔鏡は体に1CM未満の小さなポート(穴)を開けて、そこから機械を挿入し、腹腔内で手術を行う方法です。傷の小ささから、体へのダメージを最小限に留めることができるため、日帰り手術が可能ですし、痛みもとても少なく実施できます。お腹のなかを直接カメラでみますので、精巣の位置が把握しやすいところも長所のひとつです。
以下手術写真となりますのでご注意ください
体外に出ずに膀胱の横にとどまっている精巣(右精巣)
左横腹からポートを設置し、精巣をつまみ上げます
右横腹びポートから電気メスのような止血切断デバイスを用いて、精巣の血管を処理、切断します
腹腔内陰睾は腹腔鏡がおすすめです!
病気の予防手術であっても、動物さんへの痛み・ダメージがすくないに越したことはありません。
腹腔内陰睾でお困りの際はぜひ動物医療センター元麻布にご相談ください!
執筆:川﨑優梨